
6月18日は「おにぎりの日」です。記念日の意味や由来、記念日を盛りあげる豆知識やクイズ、写真素材をい紹介しています。記念日を使った「イベントのアイデア」「情報発信の素材」「暮らしを楽しむ知恵」としてご利用下さい。
6月18日「おにぎりの日」の 意味・由来
おにぎりの日は、1987年に日本最古の「おにぎりの化石」が石川県鹿島郡鹿西町(現在の中能登町)で、発見されたことにちなんで制定されました記念日です。
日付は、「鹿西(ろくせい)」の「ろく(6)」と毎月18日の「米食の日」と合わせたものになります。

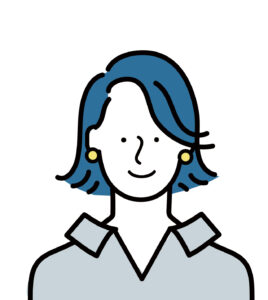
人々は古くからおこめを握って食べていたんですね
参考:日本記念日協会 https://www.kinenbi.gr.jp/
おにぎりの豆知識・雑学・クイズ
おにぎりにまつわる豆知識をピックアップしました。記念日を盛り上げるクイズなどにつかってみてくださいね。
- 問題①おにぎりの具材として、日本で最も古くから親しまれているとされるのはどれ?
A. 梅干し
B. 鮭
C. 昆布 - 正解:A梅干し
日本で最も古くから親しまれているおにぎりの具材は「梅干し」です。鎌倉時代の承久の乱の際、梅干し入りのおにぎりが兵士たちの携行食(兵糧)として用いられたことがきっかけで、その存在が広まりました。保存性が高く、殺菌効果もある梅干しは、長期保存や持ち運びに適していたため、当時の戦において理想的な具材だったのです。こうした歴史背景から、梅干しはおにぎりの定番具材として、現在まで長く親しまれています。
- 問題②「とろろ昆布おにぎり」が有名な都道府県は?
A. 福岡県
B. 山形県
C. 富山県 - 正解:C富山県
「とろろ昆布おにぎり」が有名なのは富山県です。富山では、おにぎりに海苔ではなくとろろ昆布を巻くのが定番スタイル。昆布の消費量は全国でもトップクラスですが、実は県内で昆布はほとんど採れません。江戸時代、北海道の昆布を運んできた北前船が富山に寄港したことや、明治時代に北海道へ移住した富山県民が故郷に昆布を送ったことが、昆布文化の定着につながりました。酸味と旨みが絶妙なとろろ昆布は、白米との相性も抜群です。
- 問題③「ばくだんおにぎり」と呼ばれるジャンボサイズのおにぎりが有名な都道府県は?
A. 北海道
B. 新潟県
C. 島根県 - 正解:C島根県
「ばくだんおにぎり」が有名なのは島根県・隠岐の島です。隠岐の島は日本海に浮かぶ自然豊かな諸島で、特に冬に収穫される「岩のり」が名産品です。北風が吹く12月から2月にかけて、地元の人々が岩場に生えたのりを手作業で摘み取る「のり摘み」は、隠岐の冬の風物詩として知られています。この岩のりは繊維が太く、歯ごたえが良く、香り高いことで評判。地元では正月に食べる「岩のり雑煮」に欠かせない存在です。
この岩のりをたっぷり使い、大きく丸く握ったおにぎりに巻いたものが「ばくだんおにぎり」。その名の通り爆弾のような見た目をしており、食べ応えも抜群です。地元では弁当や軽食として親しまれており、観光客にも人気のご当地グルメ。海と暮らしが密接に結びついた隠岐の島ならではの味わいを楽しめる逸品です。
参考:農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/gohan-1.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/bakudanonigiri_shimane.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/37_7_toyama.html
商用フリー・無料で使えるおにぎりの写真
おにぎりをテーマにした写真を、商用利用もできるフリー素材 photoACからピックアップしました。「ブログやポスターなどに使ってみたいな~」と思ったら、photoAC(無料)からダウンロードしてご利用ください。
なおダウンロードは「PhotoAC」からお願いします。写真をクリックしていただくと、外部リンク先よりダウンロードができます。

お気に入りの具材でおにぎりを楽しもう
おにぎりの日にちなみ、おにぎりがより美味しく楽しめる海苔や具材にこだわってみては。
まとめ
歴史や地域性にも触れられる「おにぎり」は、まさに日本のソウルフード!6月18日「おにぎりの日」は、お気に入りの具材で「おにぎり記念日」を楽しんでみませんか?




